 |
来日15年、日本人以上に日本語にくわしい ポンフェイ博士ならではの 面白エピソード満載! |
|
「日本人、ここが嫌い、ここが好き」
「ここが不思議、ここがわからない日本人」 在日外国人100人を対象とした 特別アンケートの結果も、大公開! |
|
| この他、日本文化・経済への提言、 日本人にも説明できない数々の不思議を ポンフェイ博士が一刀両断! これであなたもちょっとした゛日本語通"! |
|
【'99 6月 月刊「日本語」6月号(アルク出版) より抜粋】 日本人の常識に呈される疑問 多忙な人である。原稿執筆はもちろん、講演会、ラジオ番組出演など、さまざまな仕事をこなす。しかも、その活動範囲は日本だけでない。事実、この取材を申し込んだ日には、上海で「日本文化と中国文化−大阪ことばのおもしろさ」と題する講演を行った。
現在はこんな超多忙な彭さんだが、日本語に興味を持ったのは小学生の頃。ふとしたことから日本人に「こんにちは」を教えてもらったのが、そもそものきっかけだった。中学2年のときには、ラジオ講座を聞きながら独学で勉強し、復旦大学に進んでからは本格的に日本語を学んだ。
(中略) |
|
【'99 5月18日 CHINESE DRAGON(中国情報専門紙)より抜粋】
「歓迎したいと思います」「お詫びしたいと思います」「お悔やみしたいと思います」のような切なる気持ちをその場で特定の人に向けて表す場合、「・・・したいと思います」の形をとると、いつ歓迎するか、いつお詫びするか、いつお悔やみするかとの疑問と誤解を生じることもあると指摘している。また、日本語の中に罵倒語がわりあいに少ない。英語や中国語に比べると、驚くほど少ない。ところが反面、反語的表現が多い。「いいかげん」「ええかげん」は本来、「よいほどあい」「適当」の意味だが、人を責める場合の「いいかげん」は「よい具合」という意味にはならない。「傑作」「結構なご身分」もそうだ。日本語の「けしからん」も昔、いい意味のことばで、悪いことに対しては使われなかったと著者が分析している。(中略) 著者は日本語の「気配り表現」について詳しく論じている。日本語の中で「敬語」よりも「気配り表現」を使いこなせないと、いわゆる国内摩擦を引き起こす。だが、国際交流の舞台で使うと、今度は国際摩擦を引き起こす。著者はさらに「人間は気配り表現を作った。気配り表現がまた、人間の思考方式、行動様式、習慣を作っている。気配りがプラスに働くと人間関係がよい状態に保つことができるが、マイナスに働くと、人間関係を厄介にすることさえある。気配りによってがんじがらめにされ、動けなくなることも実際に多くみられる。日本の改革はまさにここから考え直す必要があるのではないだろうか」と提言している。習慣の違いについて各国の数多くの例が取り上げられた。面白い例には「洗顔における日本と中国の違い」「写真を撮る際の掛け声」などがある。 本書で在日外国人と100人の「好きな日本人と嫌いな日本人」「好きな外国人ときらいな外国人」のアンケート調査の結果を初公開、さらに徹底的に分析を加えた。「ごうまんな態度の日本人に出会ったことがありますか」「日本で1番腹が立ったこと、不愉快なことは何か」「日本で1番感動したことは何でしょうか」「日本人とは付き合いやすいと思いますか」「どんな日本人なら2度と付き合いたくないのか」などストレートな質問が多かった。 そういう身近な問題から始めて、日本人の言葉使いの特徴、風俗習慣のさまざまな現象を取り上げ、ふだん日本人が気がつかないでいることを鮮明に浮き彫りにする。 日本人の考えを辛口で語る場合もあるが、全体としては温かいまなざしとユーモラスな語り口が行き渡る。本の終章は「疲れきった日本人の、明日への提言」。日本の経済、文化、若者、教育、ストレス解消産業開発、アジアとの交流などの提言も傾聴に値する。ぜひともご一読を。 |
| 【'99 3月29日 産経新聞 記事より抜粋】 日常に潜む不思議を探る 白鳥女子短大学長 山折哲雄氏 |
|
|
とにかくユニークな人物である。彭飛さんは中国上海に生まれ、大阪の大学で日本語を研究して文学博士になった。標準語と大阪弁を駆使して新聞・テレピ・講演などで大活躍、先年、『「ちょっと」はちょっと・・・日本語の不思議』を書いてマスコミの話題を呼んだ。地域の国際交流にも積極的で、その助言は人びとに刺激を与えてきた。「ポンポン・クラブ」というファンの集まりができ、日中民間外交の面でも楽しい輪をひろげている。 |
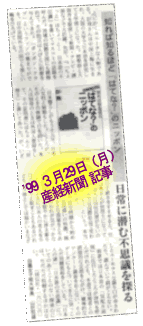 |
|
【'99 2月7日 読売新聞 記事より抜粋】 「結構です」はYES?NO?ニッポンの「なぜ」つづる |
 |
| 今回の著書はいわば第3弾。いわく、▽なぜ「お2階」といっても「お3階」とは言わないのか▽なぜ
お礼を言われて「とんでもない」と返答するのか▽「結構です」とは、YESなのか、NOなのか・・・。 確かに、料理店などで「お2階へどうぞ」と案内されることはあっても、3階の場合、「お」はつかない。<日本の昔の建築構造に2階建ての建物が多かったための、独特の言い方なのだろうか>と博士は疑問を投げかける。 博士がもっとも困惑したのは「気配り表現」で、「結構です」の使い方もその一つ。「結構なお日和で」と肯定的に使われることもあれば、コーヒーか何かを勧められたときに言えば、「要らない」という否定の意味になる。その違いが理解しがたかったという。 おう盛な好奇心と観察力を感じさせる指摘が平易な語り口の随所に光っていて、「そういえばそうだな」とうなずかされたり、思わずにやりとさせられたり。<身内への話、アイディアとして受け止めてほしい>という、終章の「疲れきった日本人への、明日への提言」も傾聴に値する。 |
|
| 出版社 |
祥伝社 |
| 定 価 |
1680円(本体1600円) |
|
刊行日 |
1999年2月3日 |
| 戻る |
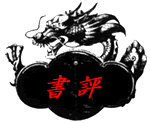 (略)朝日新聞や産経新聞の300回ほどの好評連載コラムに大幅加筆したものである。
この本では難解な日本語として数多くの例が取り上げられている。(中略)
(略)朝日新聞や産経新聞の300回ほどの好評連載コラムに大幅加筆したものである。
この本では難解な日本語として数多くの例が取り上げられている。(中略)